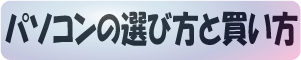コンピューター
最終更新日
2023年09月07日
コンピューターとは
基礎
コンピューターとは指示通りに計算処理を行う機械です。電子計算機と呼ぶ場合もあります。家庭で使用するコンピューターと言えばパソコン(パーソナル・コンピューター)が有名ですが、スマートフォン、家庭用ゲーム機、電卓等、これらもコンピューターに該当します。昔はコンピューターとは人間の職業名
今ではコンピューターと聞くと人のイメージが出てきませんが、昔はコンピューターとは人間の職業名でした。手計算、または手動式計算器を使用し計算を行っていた頃、これらを仕事として行っていた人達をコンピューターと呼びました。コンピューターの5大装置
コンピューターの5大装置とは
コンピューターはそれぞれ機能が異なる複数の装置で構成です。演算装置、制御装置、記憶装置、入力装置、出力装置、これら5つの装置が基本です。これらの装置がコンピューターの5大装置です。各装置の機能は名称のとおりです。演算装置はデータを演算する、制御装置は各装置を制御する、記憶装置はデータを記憶する、入力装置はデータを入力する、出力装置は演算した結果等を出力する機能があります。演算装置
演算装置は算術論理演算装置の略です。英語にするとArithmetic and Logic Unitです。略してALUです。四則演算、論理演算を行います。中央演算処理装置
コンピューターは演算装置と制御装置が組み合わさった装置を搭載する場合が多く、このような装置を中央演算処理装置やCPU(Central Processing Unit)と呼びます。主記憶装置、補助記憶装置
記憶装置は主記憶装置と補助記憶装置に分かれている場合が多いです。主記憶装置は一次記憶装置、補助記憶装置は二次記憶装置と呼ぶ場合もあります。主記憶装置はデータアクセス速度が速いですが、電源が切れるとデータが消えます。補助記憶装置はデータアクセス速度が遅いですが、電源が切れてもデータが消えません。演算装置が演算に利用するデータは、高速に演算できるように補助記憶装置から主記憶装置へ移します。パソコンのPCパーツ
パソコンが搭載するPCパーツの中で、メインメモリーが主記憶装置、HDDやSSD等のストレージが補助記憶装置に該当します。CPUは演算装置と制御装置です。キーボード、マウス、マイク、スキャナー等は入力装置です。ディスプレイ、スピーカー、プリンター等は出力装置です。コンピューターの種類
ノイマン型コンピューター
ノイマン型コンピューターとは、演算装置、制御装置、記憶装置、入力装置、出力装置で構成し、記憶装置に保存したプログラムに従って処理を実行するコンピューターです。フォンノイマン型コンピューターと呼ぶ場合もあります。米国の数学者ジョン・フォン・ノイマンが考案したのでノイマン型です。ノイマン型コンピューターを基本としてコンピューターが発展してきたので、ほとんどのコンピューターがノイマン型コンピューターに該当します。非ノイマン型コンピューター
非ノイマン型コンピューターとは、ノイマン型コンピューターにはない特徴を持つコンピューターです。非フォンノイマン型コンピューターと呼ぶ場合もあります。例えば実用化に向けて研究中の段階ですが量子コンピューターが該当します。アナログ・コンピューター
アナログ・コンピューターとは、電圧の値で数値を表現し扱うコンピューターです。例えば1を1V、2を2Vで表現します。デジタル・コンピューター
デジタル・コンピューターとは、電圧が低いか高いかで0と1の数値を表現し扱うコンピューターです。例えば0を0V、1を10Vで表現します。0と1のみですが、他の数値を2進数を利用して表現します。フォールトトレラント・コンピューター
フォールトトレラント・コンピューターとは、誤作動や故障が起きても停止せず正常に動作し続けるコンピューターです。無停止型コンピューターと呼ぶ場合もあります。例えば複数台のコンピューターをネットワークで接続して分散処理し、1台に故障等が発生したら停止し他のコンピューターが分散処理し続けるシステムは、全体として見ればフォールトトレラント・コンピューターに該当します。メインフレーム
メインフレームとは、大企業の基幹業務や大学の研究等で使用する大規模コンピューターです。ホスト・コンピューター、汎用コンピューター、汎用大型コンピューター、汎用機等と呼ぶ場合もあります。一般的に個人が所有するパソコン等のコンピューターよりも遥かに高性能です。スーパー・コンピューター等と違い、特定の用途に限らず汎用的に使用可能です。
オフィス・コンピューター
オフィス・コンピューターとは、メインフレームと同様に使用するコンピューターだが、メインフレームよりも規模が小さいコンピューターです。オフコンと略す場合があります。ミッドレンジ・コンピューター、ミニコンピューター、ワークステーション等と呼ぶ場合もあります。主に中小企業の事務処理で使用するコンピューターとして普及しました。ミッドレンジ・コンピューター
ミッドレンジ・コンピューターとは、メインフレームとパソコン、両者の中間に位置するコンピューターです。パソコンでは不十分だがメインフレームほどの規模が不要な用途に使用する企業や大学向けのコンピューターです。例えば企業や大学に設置し、多数のクライアント・コンピューターが接続し使用するホスト・コンピューターがミッドレンジ・コンピューターに該当します。スーパーコンピューター
スーパーコンピューターとは、一般的なコンピューターより遥かに高性能なコンピューターです。スパコン、ハイパフォーマンス・コンピューターと呼ぶ場合もあります。物理学、天文学、化学、生物学、地球惑星科学、気象学、工学等、これらの分野で大規模なシミュレーションの実行が主な用途です。超並列コンピューター
超並列コンピューターとは、大量のマイクロプロセッサーを搭載した高性能コンピューターです。スーパーコンピューターと似ていますが、超並列コンピューターではパソコン用マイクロプロセッサー搭載です。スーパーコンピューターではそれ専用のマイクロプロセッサー搭載です。パソコン用マイクロプロセッサーの使用でコストを抑えられます。グリッド・コンピューター
グリッド・コンピューターとは、ネットワークに接続している大量のコンピューターが連携し動作するコンピューターです。1台の高性能コンピューターのように処理を行いますが、実際にはグリッド・コンピューターを構成する各コンピューターが手分けして処理を行います。ホスト・コンピューター、クライアント・コンピューター
ホスト・コンピューターとは、ネットワークに接続しているコンピューターの中で、特定の処理を担当するコンピューターです。ホストと略す場合があります。クライアント・コンピューターとは、ホスト・コンピューターに接続し特定の処理の依頼をするコンピューターです。クライアントと略す場合があります。例えば家庭に複数のコンピューターを接続するネットワークを構築します。その内の1台をテレビ番組の録画、削除、管理等、テレビ機能の処理を担当としますが、これがホスト・コンピューターに該当します。別のコンピューター、例えばノートパソコンやスマートフォンからホスト・コンピューターにアクセスし、録画等を依頼可能としますが、これらがクライアント・コンピューターに該当します。
サーバー、クライアント
ホスト・コンピューター、クライアント・コンピューターと同じ意味と認識してよいです。ホストとサーバー、どちらの用語を使用するか定義がありますが、統一した定義がありません。例えばクライアントを使用するには特定の処理担当のコンピューターへの接続が必要な場合はそのコンピューターをホストと呼び、接続が不要の場合はそのコンピューターをサーバーと呼ぶ定義があります。特定の処理担当のコンピューターの規模が大きいとホスト、規模が小さいとサーバーと呼ぶ定義があります。特定の処理担当のコンピューターが1台の場合はホストと呼び、複数台の場合はサーバーと呼ぶ定義があります。これらの定義通りに用語を使用しなくても間違いではありません。パーソナル・コンピューター
パーソナル・コンピューターとは個人向けのコンピューターです。ワークステーション
ワークステーションとは、個人向けの高性能コンピューターです。ネットワーク・コンピューター
ネットワーク・コンピューターとは、ネットワーク接続を前提に使用するコンピューターです。英語ではNetwork Computerであり、略しNCと呼ぶ場合があります。ネットワークに接続しないと全く使用できないか、ほとんど使用できません。トラステッド・コンピューター
トラステッド・コンピューターとは、意図したとおり動作すると信頼されたコンピューターです。サイバー攻撃に対する防御力が高く、もしサイバー攻撃を防御できなかったらユーザーに通知し被害を防ぎます。100%防ぐのが困難なので、サイバー攻撃の被害に遭い意図したとおりに動作しない可能性が残るが、通常のコンピューターよりその可能性が低いです。マイクロコンピューター
マイクロコンピューターとは、昔はマイクロプロセッサーを搭載するコンピューターを指しました。今では組込みシステムが搭載するマイクロプロセッサー(マイクロコントローラー)を指す場合が多いです。マイクロコンピューターをマイクロやマイコンと略す場合があります。レガシーフリー
レガシーフリーとは、古いインターフェースをなくしたコンピューターです。新しいインターフェースが登場すると、互換性のため古いインターフェースも搭載するコンピューターが多いです。新しいインターフェースが登場したら古いインターフェースを搭載しないコンピューターが該当します。| キャンペーン情報(PR) |
|---|
|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |