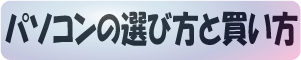電源ユニットの選び方
最終更新日
2023年09月07日
電源ユニットを選ぶ前に
販売されている電源ユニットは、主にデスクトップパソコンタワー型用
現在様々なパソコン用の電源ユニットが販売されていますが、販売されている電源ユニットは、たいていデスクトップパソコンタワー型用の電源ユニットです。タワー型以外のタイプのパソコンの電源ユニットは需要が少ないせいか、あまり販売されていません。そのため、デスクトップパソコン省スペース型や一体型、キューブ型に搭載可能な電源ユニットを探すのは結構苦労するかもしれません。デスクトップパソコン省スペース型やキューブ型でも、PC ケースがタワー型用の電源ユニットに対応していれば、市販されているタワー型用の電源ユニットを搭載できます。
デスクトップパソコン一体型は、そのパソコンの製造メーカー独自の電源ユニットが使われている事が多く、そのようなパソコンに搭載可能な電源ユニットは、まず市販されていません。しかし、入手は不可能とは限らず、メーカーに購入できないか問い合わせてみたり、中古で流通してないか探す等の手段はあります。
電源ユニット単体で購入する場合
電源ユニット単体で購入するときは、その電源ユニットを装着する PC ケースが対応する電源ユニットの規格やサイズと合う電源ユニットを選ぶ必要があります。また、規格やサイズが合っていても、PC ケースの内部構造の特性により、搭載できない電源ユニットもあります。よって、電源ユニットを単体で購入するときは、慎重に選ぶ必要があります。電源ユニットの選び方の基本
PCケース付属の電源ユニット
電源ユニットが付属しているPCケースを選ぶと、PCケースに取り付けられる電源ユニットを簡単に選べます。しっかりと調べれば電源ユニットの選び方は難しくなく、使用するCPU、マザーボード、ビデオカード等に合わせて選ぶとよいので、単体販売の電源ユニットを選ぶとよいです。巻き込み故障の考慮
電源ユニットが故障するとマザーボード等の他のPCパーツも巻き込み故障してしまう可能性があるので、しっかりとした電源ユニットを選ばなければならない。このような話をよく見聞きします。例えば、電源ユニットが故障し異常電圧もしくは異常電流がマザーボードに向かいマザーボードも故障する等、巻き込み故障する可能性があると思われます。結論を言うと、気にする必要がありません。巻き込み故障する可能性があるなら、そのことについて電源ユニットの仕様等に書かれていそうです。実際に見てみると、製品によっては仕様に保護回路が搭載されており二次被害を防ぐと記載されています。もし保護回路がないと、巻き込み故障する可能性があると思われます。
某パソコンメーカーの人に聞いてみたところ、電源ユニットが故障したパソコンの修理対応を多く行ってきたが、他のPCパーツも故障していたことが稀にあったそうです。巻き込み故障だったのかまでは解析していないそうです。自社パソコンには必ず保護回路がある電源ユニットを搭載しているので、巻き込み故障が発生する可能性が極めて低いと考えられるそうです。保護回路があっても巻き込み故障を完全に防げるわけではないので、可能性が残るそうです。
世の中には保護回路がない電源ユニットもあるかもしれず、それを使用すると巻き込み故障が発生する可能性が高いそうです。昔であれば保護回路がない電源ユニットがあっただろうが、今の時代にあるとは考えにくいそうです。
電源ユニットの規格
規格の種類
電源ユニットには様々な規格があり、各規格では本体サイズ、コネクターの種類等を規定しています。電源ユニットは対応している規格が規定している仕様を全て満たすことが必須ではありませんので、実際の仕様も確認が必要です。例えば、同じ規格でもコネクターの種類や数が製品によって違います。規格はATXが主流ですが、Flex ATX、SFX、TFX等もあり、PCケースに搭載可能な規格を選びます。ATX、ATX 12V、EPS 12V
規格のATXの後継がATX 12Vですが、ATX 12V対応でも略してATX対応とする場合が多いです。昔はATX対応でもATX 12V対応とは限りませんでしたが、今ではどの製品もATX 12Vに対応しています。今ではATX対応であれば、どの製品もATX 12VとEPS 12Vに対応しており、各規格の違いを気にせずに、これらに対応している製品を選ぶとよいです。ATX 12VO
ATX 12VOとは、+3.3V、+5V、+12V、-12V、+5VSBを+12Vのみにした規格です。ATX 12VO対応マザーボードを使用する場合、ATX 12VO対応電源ユニットを選びます。SFX
SFX対応PCケースに搭載する場合、SFX対応電源ユニットを選びます。電源ユニットの規格がSFXでも、変換ブラケットを使用しATX対応PCケースに搭載する方法があります。ATX対応電源ユニットと比べてサイズが小さくなるので、PCケース内部の空きスペースが大きくなり、PCパーツの物理的干渉がしにくい、エアフローが改善する、以上のメリットがあります。これらのメリットが必要な場合、SFX対応電源ユニットを選ぶとよいです。規格に対応している電源ユニットの呼び方
ある規格に対応している電源ユニットを「規格名+電源」と呼ぶ場合があり、幾つか例を挙げると、ATX対応の電源ユニットをATX電源、SFX対応の電源ユニットをSFX電源と呼びます。単体販売がない規格
サイズが小さい規格の電源ユニットは、単体販売が少ないです。単体販売がない場合もあります。それでも入手したい場合、ベアボーンキットまたは完成品パソコンを購入し電源ユニットを取り出す方法があります。中古品で出回っていれば、それを買う方法もあります。| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットの規格 |
電源ユニットのサイズ、ネジ穴の位置、背面レイアウト
ATX
ATXでは、サイズの幅と高さ、ネジ穴の位置が同じですが、サイズの奥行き、ファンの位置等の背面レイアウトが製品によって違います。奥行きは製品によって違いが大きく、短い方だと100mm等もあれば長い方だと200mm等もあります。
他のPCパーツと物理的干渉が発生すると搭載できませんので、PCケース内部を見て奥行きが長いと搭載できない場合、奥行きが短い製品を選びます。
PCケース背面の電源ユニットの部分は大きく穴が空いていますので、どのような背面レイアウトでも搭載できます。
個人的には見たことありませんが、大きく穴が空いておらず特定の背面レイアウトに合わせて作られている場合、搭載可能な電源ユニットが背面レイアウトによって限られますので、背面レイアウトにも注意して選ぶ必要があります。
SFX
規格が同じSFXでも、製品によってサイズ、ネジ穴の位置、ファンの位置等の背面レイアウトが違います。交換用に選ぶ場合、交換前の製品を確認しサイズ等が合う製品を選ぶとよいです。
交換用ではない場合、PCケースの電源ユニットを搭載する場所を確認し、ネジ穴同士の距離を測定すると搭載可能な幅と高さがわかります。
他のPCパーツと物理的干渉が発生すると搭載できませんので、PCケース内部を見て、何cmまで奥行きがあっても搭載できるかも確認が必要です。
PCケースの背面を見て、搭載可能なファンの位置等の背面レイアウトも確認が必要です。
組み合わせ情報を参考にして選ぶ
上記ではATX以外にSFXのみ記載しましたが、ATX以外だと選ぶのが難しいです。PCケースのメーカーが搭載可能な電源ユニットを公開している場合があり、その場合はその中から選ぶと簡単です。
パソコン関連の書籍やウェブサイトでは、様々なPCパーツの組み合わせパターンを掲載しており、同じPCケースがあればそれと組み合わせいる電源ユニットを参考にする方法もあります。
小型PCケースでは物理的干渉しやすい
Mini-ITX対応PCケース等、小型PCケースでは内部スペースが狭いので、電源ユニットと他のPCパーツが物理的干渉しやすいです。PCケースの仕様に搭載可能な電源ユニットのサイズの条件について記載があっても、他のPCパーツのサイズ等によって条件が変わる場合があります。電源ユニットと光学ドライブの物理的干渉
多くのPCケースでは電源ユニットの背面側に光学ドライブを取り付けます。電源ユニットも光学ドライブも奥行きが製品によって異なり、奥行きが長いほど物理的干渉の可能性が高まります。PCケースの仕様に記載の搭載可能な電源ユニットのサイズの条件を満たすとしても、光学ドライブの奥行きによって条件が異なる場合があります。電源ユニットとマザーボードの物理的干渉
多くのPCケースでは電源ユニットとマザーボードが物理的干渉しません。小型PCケースだとマザーボードのコネクターと物理的干渉する場合があります。電源ユニットがマザーボードの基板上を覆うように設置する場合、コネクターとの物理的干渉に注意が必要です。物理的干渉しそうな場合、奥行きが短い電源ユニットを選ぶか、サイズやコネクター配置が異なるマザーボードに変更すると解決できます。奥行きとケーブル
電源ユニットの背面から各PCパーツと接続するケーブルが出てきますので、本体からケーブルが出っ張ります。サイズの奥行きに問題なくても、背面側の空きスペースが狭いとケーブルが物理的に干渉し搭載できない場合があります。どのくらい空きスペースが必要なのかは、製品によって違いケーブルによっても違いますが、少なくとも3cm程度は欲しく、5cm程度もあればまず大丈夫です。規格のバージョンの違い
それぞれの電源ユニットの規格には、バージョンの違いによって分かれていますが、バージョンは違っても、規格は同じですので、サイズや接続方法など、基本的な部分に変更はありません。バージョンが新しくなると、以前のバージョンの問題点などが改善されているので、できるだけ新しいバージョンの規格の電源ユニットを選ぶのがおすすめです。
電源ユニットの容量
理想的な容量
容量(定格出力、最大出力、総出力、ワット数)を選ぶときに絶対に避けなければならないことは、容量不足です。パソコンの消費電力が容量を超えてしまうと、突然電源が落ちる等して不安定になったり、正常に起動しない等のトラブルの原因になります。
容量ギリギリでも同様なトラブルが発生する可能性があり、トラブルが発生しなくても電源ユニットの発熱が大きくなり寿命が早まったり冷却ファンの回転数が上がり騒音が大きくなりますので、余裕がある容量を選ぶとよいです。
消費電力が容量の50%だと最も電力変換効率が高いので、消費電力の2倍となる容量を選ぶのが理想的ですが、困難です。
様々な理由がありますが、その1つに自分が使用するときの消費電力を調べるのが困難であり、仮に調べられたとしても消費電力が一定になるように使用する人がほとんどいないと思われます。
パソコンメーカーの完成品パソコン
理想的な容量を選ぶのが難しいので、パソコンメーカーで販売されている完成品のパソコンの仕様を参考にして容量を選ぶとよいです。パソコンのPCパーツの中で特にCPUとビデオカードの消費電力が大きいので、原則的にはCPUとビデオカードが同じパソコンを参考にすればよいです。
NVIDIAのシステム電力要件
NVIDIAの公式サイトでは、自社GPUの各製品ごとにシステム電力要件(W)を公開しており、このワット数を参考に容量を選ぶ方法もあります。どのようにシステム電力要件を決めているのか非公開であり、パソコンメーカーよりは容量に余裕を持たせていません。
幾つかのNVIDIAの製品を使用しパソコンの消費電力を計測した限りでは、システム電力要件でも不足することがなく余裕がありましたので、システム電力要件を参考に選んでも大丈夫です。
容量の目安
あらゆるPCパーツの構成で容量の目安を掲載するのは困難ですが、一部の構成の場合における容量の目安を以下に記載します。一般的な高性能CPUであればTDPが100W程度、消費電力は余裕を見て150W程度です。
一般的にメインメモリーが数枚、マザーボードが1台、ストレージが2台、光学ドライブが1台ですので、これらの消費電力は余裕を見て100W程度です。
ビデオカードは製品によって消費電力の違いが大きいので、この違いも考慮すると容量の目安は以下のとおりです。
| ビデオカードの 消費電力 |
パソコン全体の 消費電力 |
電源容量の目安 |
|---|---|---|
| 50W | 300W | 400W〜450W |
| 100W | 350W | 500W〜550W |
| 150W | 400W | 550W〜600W |
| 200W | 450W | 600W〜650W |
| 250W | 500W | 700W〜750W |
| 300W | 550W | 750W〜800W |
| 350W | 600W | 850W〜900W |
| 400W | 650W | 900W〜950W |
| 450W | 700W | 1000W〜1050W |
| 500W | 750W | 1050W〜1100W |
最高クラスの性能を持つCPUだとTDPが100Wを大きく超え、消費電力でも150Wを大きく超えます。
このようなCPUを搭載する場合は、上記の容量の目安では足りなくなる可能性が高いので、パソコンメーカーの完成品パソコンを参考にするとよいです。
| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットの容量 |
電源ユニットの系統
電源ユニットの系統には+3.3V、+5V、+12V、-12V、+5VSBがあり、各系統でも出力不足にならないように選ぶ必要があります。
+12Vが1系統だとシングルレールと呼びますが、この場合は適切に容量を選べば、まず各系統で出力不足になりません。
+12Vが複数系統だとマルチレールと呼びますが、この場合は適切に容量を選んでも、+12Vの各系統で出力不足になる可能性が出てきます。
単純な例ですが、+12Vが2系統あり各系統の最大出力が250Wの場合、消費電力が300Wのビデオカードを使用すると出力不足になります。
マルチレールの場合、+12Vにて出力電力に大きな変動があっても他の+12Vに与える影響が小さく、安定性が高まるメリットがありますので、昔はマルチレールが主流でした。
今では技術進歩によりシングルレールでも安定性が高いので、シングルレールが主流です。
マルチレールだと+12Vの各系統で出力不足になる可能性がありますので、シングルレールを選ぶとよいです。
+12Vが1系統だとシングルレールと呼びますが、この場合は適切に容量を選べば、まず各系統で出力不足になりません。
+12Vが複数系統だとマルチレールと呼びますが、この場合は適切に容量を選んでも、+12Vの各系統で出力不足になる可能性が出てきます。
単純な例ですが、+12Vが2系統あり各系統の最大出力が250Wの場合、消費電力が300Wのビデオカードを使用すると出力不足になります。
マルチレールの場合、+12Vにて出力電力に大きな変動があっても他の+12Vに与える影響が小さく、安定性が高まるメリットがありますので、昔はマルチレールが主流でした。
今では技術進歩によりシングルレールでも安定性が高いので、シングルレールが主流です。
マルチレールだと+12Vの各系統で出力不足になる可能性がありますので、シングルレールを選ぶとよいです。
| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットの系統 |
騒音レベル
静音性を重視するなら
電源ユニットは、パソコンから発生する騒音源の一つです。電源ユニットにある冷却用ファンの音や振動音が原因ですが、電源ユニットによっては、ヒートシンクを用いてファンレスを実現したり、特殊な素材や部品を用いて振動音を抑えています。騒音レベルが、単位 dB(デシベル)を使って数値で表記されていれば、静かさがわかりますが、どの電源ユニットにも書かれているとは限りません。もし書かれていた場合は、20 dB 台であれば静音性を重視した電源ユニットと言えます。
特に総出力ワット数が多い電源ユニットほど、発熱量が多くなり、冷却ファンなどによる騒音レベルが高くなりやすいですので、総出力ワットが大きい電源ユニットを選ぶときは、表記されていれば騒音レベルを確認し、電源ユニットの特徴が記載されている仕様が見られるのであれば、冷却システムに工夫をし、静音性を重視しているかについても注目するのがおすすめです。
電源ユニットのコネクター
電源ユニットに必要なコネクターの種類があるのか、必要なコネクターの数があるのか確認して選ぶ必要があります。
交換用の電源ユニットを選ぶ場合、交換前の電源ユニットで使用していたコネクターが全てある電源ユニットを選ぶ必要があります。
交換前の電源ユニットに独自のコネクターがあり使用していた場合、代用できる電源ユニットの入手が難しくなります。
高性能CPUとそれを搭載可能なマザーボードでは消費電力が大きいため、ATX 12Vコネクター(4ピン)とEPS 12Vコネクター(8ピン、4+4ピン)それぞれ1個ずつ合計2個や、EPS 12Vコネクター(8ピン、4+4ピン)を2個必要とする場合が多いです。
EPS 12Vコネクター(8ピン、4+4ピン)が2個ある製品を選ぶと、あらゆるマザーボードやCPUに対応できます。
ピン数には6ピン、8ピン、16ピンがあります。8ピンは6ピンと2ピンに分離可能なので6+2ピンと呼ぶ場合もあります。16ピンは分離可能ではないですが、それぞれ役割が異なる12ピンと4ピンが一体なので12+4ピンと呼ぶ場合もあります。16ピンを12VHPWRと呼ぶ場合もあります。
ビデオカードが必要とするコネクター数が製品によって異なります。6ピン、8ピンに限れば、最大で6ピン+8ピン+8ピンです。8ピンが2個、6ピンが1個ある電源ユニットを選ぶと、あらゆるビデオカードに対応できます。
16ピンがあるビデオカードの場合、最大16ピンが1個です。
交換用の電源ユニットを選ぶ場合、交換前の電源ユニットで使用していたコネクターが全てある電源ユニットを選ぶ必要があります。
交換前の電源ユニットに独自のコネクターがあり使用していた場合、代用できる電源ユニットの入手が難しくなります。
CPU補助電源コネクター
使用するマザーボードやCPUが必要とするCPU補助電源コネクターの種類や数を調べ、不足しないように製品を選ぶとよいです。高性能CPUとそれを搭載可能なマザーボードでは消費電力が大きいため、ATX 12Vコネクター(4ピン)とEPS 12Vコネクター(8ピン、4+4ピン)それぞれ1個ずつ合計2個や、EPS 12Vコネクター(8ピン、4+4ピン)を2個必要とする場合が多いです。
EPS 12Vコネクター(8ピン、4+4ピン)が2個ある製品を選ぶと、あらゆるマザーボードやCPUに対応できます。
PCI Express用コネクター
PCI Express接続の拡張カード用の補助電源コネクターです。実質ビデオカード用なのでビデオカード補助電源コネクターとも呼びます。使用するビデオカードが必要とするコネクター数を調べ、不足しないように選びます。複数枚のビデオカードを搭載する場合、複数枚分のコネクター数が必要です。ピン数には6ピン、8ピン、16ピンがあります。8ピンは6ピンと2ピンに分離可能なので6+2ピンと呼ぶ場合もあります。16ピンは分離可能ではないですが、それぞれ役割が異なる12ピンと4ピンが一体なので12+4ピンと呼ぶ場合もあります。16ピンを12VHPWRと呼ぶ場合もあります。
ビデオカードが必要とするコネクター数が製品によって異なります。6ピン、8ピンに限れば、最大で6ピン+8ピン+8ピンです。8ピンが2個、6ピンが1個ある電源ユニットを選ぶと、あらゆるビデオカードに対応できます。
16ピンがあるビデオカードの場合、最大16ピンが1個です。
| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットのコネクター |
電源ユニットのケーブル
ケーブルの種類
ケーブルの配線がしやすい、整理がしやすいメリットがあるので、プラグインタイプでありスリーブケーブルを選ぶとよいです。プラグインタイプではなく直付けタイプであったり、スリーブケーブルではなくても問題があるわけではありませんので、気にせずに選んでもよいです。
ケーブルの長さ
電源ユニットと各PCパーツの位置、PCケースの大きさ、配線方法によってはケーブルの長さが足りなくなります。各製品のケーブルの長さは大体同じであり、自分にとって合うケーブルの長さがある製品を選ぼうとしても選べません。
ケーブルの長さが足りない場合は、延長ケーブルを使用する方法があります。
| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットのケーブル |
電源ユニットの80PLUS
80PLUS認証取得の有無
電源ユニットの変換効率が高いと無駄な消費電力と発熱が減り、低消費電力により電気代の節約、発熱による劣化低減、低発熱により静音性の向上につながります。電源ユニットに高い負荷がかかり長時間使う場合は、変換効率の差が電気代に結構影響します。電源ユニットの部品の中で特にコンデンサーが熱により劣化しやすく、変換効率が高いと発熱が小さく劣化を抑えられ寿命が延びます。多くの電源ユニットはファンの回転数が発熱に応じて変わり、変換効率が高いと発熱が小さく温度が上昇しにくいので、ファンの回転数の上昇も抑えられ静音性が向上します。変換効率を重視する場合は80PLUS認証を取得している電源ユニットを選ぶとよいです。変換効率が高いほどコストがかかり価格が高いので、変換効率と価格のバランスを考慮して選ぶとよいです。変換効率が高いほど無駄な消費電力が減り、節約できた電気代で多少は回収できることも考慮して、価格が高くても選ぶか決めるとよいです。特にパソコンを常時高負荷で長時間使用し続ける場合は、完全に回収できなくても結構な電気代の節約になります。その場合は変換効率の高さ重視で選ぶとよいです。
同じ80PLUSのランクにおける変換効率の違い
80PLUSのランクが同じでも電源ユニットによって変換効率が違い、様々な電源ユニットの変換効率を公開しているウェブサイトがあり調べられます。少しでも変換効率が高い方を選びたい場合は参考になりますが、個体差がありますのであまり気にする必要がありません。例えば、某電源ユニットは80 PLUSシルバー認証を取得しているが、個体差があり中には80 PLUSゴールド認証を取得できるほど変換効率が高く、これくらい違いが出る場合があります。実際に購入し調べないと、どのくらいの個体差があるのかわかりませんので、80PLUSのランクに注目して選べばよいです。
価格と変換効率のバランスがよい80PLUSのランク
今のところ80PLUSゴールドが価格と変換効率のバランスがよいです。価格の安さを重視する場合、80PLUSスタンダード(無印)、80PLUSブロンズ、80PLUSシルバー、これらが選択の目安です。変換効率の高さを重視する場合、80PLUSプラチナ、80PLUSチタンが選択の目安です(2022/07/29時点)。| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットの80PLUS |
電源ユニットの入力電圧
90Vを動作保証
日本国内の電源コンセントの電圧は100Vですが、電圧降下が発生する場合があり、その場合でも正常に動作するように90Vを動作保証している製品を選ぶとよいです。電圧は変動するものなので、一般的に日本国内向けの家電製品は電圧が90〜110Vでも正常に動作するように作られています。電源ユニットも例外ではなく、日本国内向けに販売されている100V対応製品であれば、90Vを動作保証しています。ワールドワイド向け
ワールドワイド向けとは、日本に限らず様々な国の電圧に対応していることを意味します。入力電圧が115Vと230Vに対応しています。定格電圧の上下10%までは誤差が認められており、諸外国の多くの商用電源電圧範囲110V〜125Vと220V〜250Vをカバーできます。誤差10%なので下限の電圧は以下のとおり計算でき、日本の電圧100Vをカバーしていない電源ユニットもあります。一般的には90Vを動作保証しています。115V×0.9=103.5V
90Vを動作保証しておらず、100Vや110Vを動作保証としている製品があります。それでも多少の電圧降下があっても正常に動作する可能性が高いですが、90Vを動作保証している製品を選ぶのが望ましいです。
115Vか230Vに設定するスイッチ
昔と違って今ではあまり見られませんが、入力電圧の115Vと230Vに対応かつ手動で設定を行う電源ユニットがあります。これを選んでも問題がなく、選び使用する場合は本体背面にある115Vか230Vの設定に使用する赤い色のスイッチに注意が必要です。日本国内では電源コンセントの電圧が100Vなので115Vに設定します。両者の電圧が違いますが、一般的には115Vよりも80〜85%低い電圧でも動作するように設計されています。
230Vに設定し使用すると危険です。最悪電源ユニットに限らず他のPCパーツも故障します。自動的に電力の供給を遮断する機能があり、たいていは起動しないだけで済みますが、絶対に防げるとは限りません。
電源ユニットの入力電流
15A
一般的に家庭用コンセントが100V/15Aであり、多くの電源ユニットが使用可能です。電源ユニットによっては容量が大きいのが原因で使用できないので、1,000Wを大きく超える大容量の製品を選ぶときは使用可能なコンセントに注意が必要です。例えば、容量が1,500Wある某製品では最低でも100V/18Aのコンセントが必要です。この某製品は80 PLUSゴールド対応であり変換効率が最低でも87%です。コンセントから得ようとする最大電力を計算します。1,500W÷0.87≒1,724W
1,724Wを100Vで割ると約17Aであり、最低でも100V/18Aのコンセントであれば過負荷になりません。最大出力が1,500Wよりも低く、コンセントから得ようとする電力が1,500W以下であれば、100V/15Aのコンセントでも大丈夫です。例えば、最大出力が1,000W程度であれば、仮に変換効率が80 PLUSスタンダードの80%でも、100V/15Aのコンセントから得ようとする電力が1,250Wとなり過負荷になりません。
ただし、最大出力を正確に見積もるのが難しいので危険です。正確に見積もれたとしても、CPU等が異常動作し最大出力が異常に高くなる可能性があり危険です。コンセントが過負荷になると火災につながる恐れがありますので、使用可能なコンセントの条件を守るとよいです。
瞬断対策
一般的には電源ユニットで瞬断が問題になりません。問題になるとパソコンの電源が突然落ちます。例えば、UPS(無停電電源装置)を使用し、切り替え時に瞬断が発生し問題になる場合があります。
UPSを例に挙げましたが、UPSによって瞬断時間が違い、長いUPSでも10ms程度です。ほとんどの電源ユニットでは問題になりません。問題になる場合、瞬断時間が短いUPSを使用するか、瞬断対策に優れ瞬断時間が長くても問題ない電源ユニットを使用します。大容量コンデンサーを搭載し約20msの瞬断に耐えられる電源ユニットもあります。
UPSを例に挙げましたが、UPSによって瞬断時間が違い、長いUPSでも10ms程度です。ほとんどの電源ユニットでは問題になりません。問題になる場合、瞬断時間が短いUPSを使用するか、瞬断対策に優れ瞬断時間が長くても問題ない電源ユニットを使用します。大容量コンデンサーを搭載し約20msの瞬断に耐えられる電源ユニットもあります。
電源ユニットの保護回路
電源ユニットは、過電圧、過電流、過温度等から保護する回路を搭載しており、電源ユニットに限らず他のPCパーツも故障等しないように守る重要な機能です。
どの製品も搭載しているとは限らず、容量等が同程度の製品の中で価格が安い方の製品だと、保護回路を搭載していない場合があります。
平均的な価格以上の製品であれば保護回路を搭載していると思われますが、必ず保護回路がある製品を選びたい場合は、仕様等を見て保護回路搭載か確認して選ぶとよいです。
どの製品も搭載しているとは限らず、容量等が同程度の製品の中で価格が安い方の製品だと、保護回路を搭載していない場合があります。
平均的な価格以上の製品であれば保護回路を搭載していると思われますが、必ず保護回路がある製品を選びたい場合は、仕様等を見て保護回路搭載か確認して選ぶとよいです。
| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットの保護回路 |
電源ユニットのファン
ファンレス
ファンレスだと冷却用のファンがないため、ファンから発生する騒音がなく静音性に優れており、静音性重視の場合は選ぶとよいです。単にファンレスを選べばよいわけではなく、他のPCパーツの発熱や冷却、使用環境の温度も考慮し、電源ユニットがファンレスでも異常な高温にならないようにする必要があります。
ファンレスではなくても十分静かなので、原則的にはファンがある電源ユニットを選ぶとよいです。
準ファンレス
準ファンレスだと冷却用のファンがありますが、ファンの回転が停止しファンレスのように動作が可能です。ファンの回転が停止する条件は製品によって違い、一定の温度以下ではファンが停止する、一定の出力以下ではファンが停止する等の条件があります。
冷却性能を高める必要があるときはファンによる騒音が発生してもやむを得ないが、そうではないときはファンレス動作で静音にしたい場合、準ファンレスを選ぶとよいです。
ファン動作モード
電源ユニットの中には、ファンの動作モードを設定できる製品があります。様々な動作モードがありますが、例えば冷却重視で常に最大回転数で動作するモードや、静音重視で出力電力が一定以下であれば回転を停止するモードがあります。
自分の用途に合わせて設定したい場合、ファンの動作モードを設定可能な製品を選ぶとよいです。
ファンの口径
ファンの口径が大きいほど風量が大きく、低速回転でも冷却性能を高くでき静音性に優れます。静音性を重視する場合、ファンの口径が大きいとよいです。
と言っても選択肢はATX電源だと120mmか140mm程度であり、他の要因でも静音性が変わりますので、ファンの口径をあまり気にする必要がありません。
ファンの口径だけではなくファンの羽根のサイズ、形状、枚数も静音性に影響しますが、これらも比較して優劣を判断するのは困難です。
ファンのベアリング(軸受け)
電源ユニットのファンのベアリング(軸受け)には、大まかに分けてスリーブベアリング、ボールベアリング、流体軸受けがあります。流体軸受けは英語で言うとFluid Dynamic Bearingであり、それぞれの頭文字を取ってFDBと略して呼ぶ場合があります。
電源ユニットのファンは、寿命、静音性、コストが重要ですが、寿命が長い順に並べると、流体軸受け、ボールベアリング、スリーブベアリングです。
静音性に優れる順に並べると、流体軸受け、スリーブベアリング、ボールベアリングです。
コストが安い順に並べると、スリーブベアリング、ボールベアリング、流体軸受けです。
ただし、電源ユニットのファンはベアリング(軸受け)が同じでも製品によって寿命、静音性、コストが違いますので、上記の順序は一概に当てはまるものではありません。
電源ユニットの部品の中でコンデンサーかファンが最も早く寿命を迎える場合が多く、寿命、静音性、コストの中で寿命を最も気にする人が多いと思われますが、それなら流体軸受けかボールベアリングを選ぶとよいです。
コストを気にせず静音性も重視するなら、流体軸受けを選ぶとよいです。
ボールベアリングでもベアリング(軸受け)から発生する騒音をできるだけ抑えていたり、大口径のファンかつ低速回転を採用する等して、静音性に優れている製品がありますが、実際に使ってみないと優れているかわかりませんので、流体軸受けを選ぶとよいです。
静音性とコストを重視するならスリーブベアリングを選ぶとよいです。
スリーブベアリングは寿命が短いですが、過酷な使用環境ではなければ電源ユニットの保証期間くらいまでは寿命を迎えることはないと期待できます。
部品
部品数
電源ユニット内部の部品数が少なかったり多かったりすることについて宣伝等に利用する場合があります。一般的には少ないとネガティブ、多いとポジティブのイメージがあるように宣伝等が利用しています。品質を高めるために部品数を多くしている場合があります。品質が下がるがコストを下げるために部品数を少なくしている場合があります。内部のエアフローをよくするためや、初期不良率や故障率を下げるために部品数が少なくしている場合があります。
部品数が少ない多いの理由は製品によって違い、どちらかの方がよいとは一概には言えません。部品数が多いか少ないか見るだけでは、電源ユニットの良し悪しがわかりません。
ホットボンド
電源ユニット内部の部品に対してホットボンドを使用していると、評価がよくない場合があります。部品の固定のために使用しており見た目はよくないですが、問題ありません。部品の発熱により溶けることがなく、通電しないので短絡(ショート)の心配もありません。コイル鳴き防止のために使用の場合もあります。コイル鳴き発生時にユーザーがホットボンドを使用する方法がありますが、保証対象外になります。
電源ユニットのコンデンサー
寿命の長さを重視する場合、許容最高温度が105度の日本製コンデンサーが採用されている電源ユニットを選ぶとよいです。
特にアルミ電解コンデンサーは寿命に大きく影響しますので日本製がよく、固体コンデンサーも影響はしますので日本製が望ましいですが、影響が小さいので海外製であってもあまり気にする必要がありません。
特にアルミ電解コンデンサーは寿命に大きく影響しますので日本製がよく、固体コンデンサーも影響はしますので日本製が望ましいですが、影響が小さいので海外製であってもあまり気にする必要がありません。
| 関連記事 |
|---|
| ・電源ユニットのコンデンサー |
電源ユニットの保証期間
電源ユニットによって保証期間が違い、1年といった短い場合もあれば10年といった長い場合もあります。
長期間に渡って使用し続ける場合、保証期間が長いとよいです。
故障率が高く寿命が短いと保証期間を長くできず、もし長くすると保証対応でコストがかかりすぎてしまいます。
保証期間が長いと故障率が低く寿命が長いとは限りませんが、そうであると期待できます。
長期間に渡って使用し続ける場合、保証期間が長いとよいです。
故障率が高く寿命が短いと保証期間を長くできず、もし長くすると保証対応でコストがかかりすぎてしまいます。
保証期間が長いと故障率が低く寿命が長いとは限りませんが、そうであると期待できます。
電源ユニットの寿命
電源ユニットの寿命は事前にわかるものではありませんが、日本製コンデンサーを採用している、保証期間が長い、以上に注目して選ぶと寿命が長いと期待できます。
電源ユニットを2〜3年使用できればよい等、短期間の寿命でもよければ、コンデンサーや保証期間について気にする必要がありません。
電源ユニットを2〜3年使用できればよい等、短期間の寿命でもよければ、コンデンサーや保証期間について気にする必要がありません。
電源ユニットのイルミネーション
内部がよく見えるオープンフレーム型PCケースを使用し、イルミネーション対応のPCパーツを搭載する楽しみ方がありますが、電源ユニットにもイルミネーション対応製品があります。
電源ユニットもイルミネーションで明るく彩りたい場合は、対応製品を選ぶとよいです。
電源ユニットもイルミネーションで明るく彩りたい場合は、対応製品を選ぶとよいです。
| キャンペーン情報(PR) |
|---|
|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |