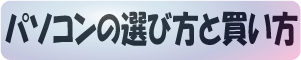SSD
最終更新日
2023年09月07日
SSDとは
基礎
SSDとはSolid State Driveの略であり、記憶媒体にフラッシュメモリーを使用する記憶装置です。エスエスディーと読みます。SSDがSolid State Diskの略とする場合もあります。SSDはHDDよりもデータ読み書き速度が速い、衝撃・振動に強い、静音性が高い、消費電力が低い、発熱が小さい、サイズが小さい、重量が軽いメリットがあります。
SSDはHDDよりも容量当たりの価格が高いデメリットがありますが、低価格化が進み小さなデメリットになりました。SSDには書き換え可能回数があるデメリットがありますが、様々な技術により気にする必要がないデメリットになりました。空き領域の断片化が進むとデータ書き込み速度が遅くなるデメリットがありますが、トリムと呼ぶ機能が登場し、気にする必要がないデメリットになりました。
パソコン等のコンピューターが使用する記憶装置にHDDが使われてきましたが、SSDのメリットが大きく、大きかったデメリットが小さくなったので、HDDの代わりにSSDが普及しました。
出典
・SSD - 意味・説明・解説 : ASCII.jpデジタル用語辞典(2010/04/19更新記事)
・ASCII.jp:安価になったSSD SSD選びと導入のポイントは? (1/3)|一度使うともう手放せない! SSDを使いこなせ(2011/08/22更新記事)
半導体メモリーを使用する記憶装置
本来はSSDが半導体メモリーを使用する記憶装置を指します。半導体メモリーとは、データを記憶できるICです。ICとはIntegrated Circuitの略であり、1つの基板に多数の素子を集め作った電子回路です。ICを作るために使用する基板がウエハーと呼ぶ半導体なので、半導体メモリーと呼びます。フラッシュメモリーを使用する記憶装置が普及し、これをSSDが指すようになりました。出典
・SSDが登場し、SATAの高速化が続く | 日経クロステック(xTECH)(2020/03/26公開記事)
フラッシュメモリー
SSD内部には記録媒体としてNAND型フラッシュメモリーを採用しています。SSDは、フラッシュメモリーにデータを記録します。
大量のフラッシュメモリー・チップを集積し大容量化を実現しています。
フラッシュメモリー・チップとは、フラッシュメモリーや他の電子部品を実装した半導体集積回路です。
SSD内部には、他にもコントローラー、バッファメモリー(DRAM)等があります。
Flash SSD
フラッシュメモリーを採用したSSDをFlash SSDと呼び、一般的にはSSDはFlash SSDを指します。フラッシュメモリー以外を用いた別種類のSSDもあり、例えばRAMを採用したSSD(ハードウェア方式のRAMディスク)があります。
SSDと偽装チップ(フラッシュメモリー・チップ)
偽装チップ問題
SSDが採用するチップ(フラッシュメモリー・チップ)が、どのメーカーのチップなのか仕様等に記載されている場合があります。SSDによっては某メーカーのチップ採用を宣伝に利用している場合があります。
一般的にSSDのユーザーがSSD内部にあるチップを確認しないですが、中には確認するユーザーもおり、偽装チップであることが判明した場合があります。
例えば、インテルのチップを採用していると謳う某SSDでは、チップにインテルのマークがない等の不審な点が見られ、チップがインテルのチップではないことが判明し、どのメーカーのチップなのか不明なことがありました。
別のインテルのチップを採用していると謳う某SSDでは、チップにインテルのマークがありましたが、存在するはずがない型番があり、偽装チップであると判明しました。
この某SSDの件で、インテルのマークがあっても正規のチップであるとは限らないとわかりました。
Colorful SSD
960GBで7980円の激安SSD発売、前モデルからIntel製チップの記載無くなる | 財経新聞 には、以下のとおり書かれています。(この記事の公開年月日は2019/07/02)廉価なSSDブランドとして知られる「COLORFUL」のSSD「SL500 960G V2」が発売された。容量は960GBで、価格は1万778円(価格.com)。秋葉原の店頭では7,980円(税別)での販売も確認されているようだ(AKIBA PC Hotline!)。採用するフラッシュメモリチップの製造元は記載されていないとのこと。なぜColorfulはSSDにIntel製チップ採用と謳わなくなったのか、その答えはColorfulに聞かないとわからないことです。
前モデルの「SL500 960G」はIntelの3D TLC NANDを採用しているとうたっていたが(パソコンSHOPアーク)、実際にはIntelブランドの使用が許されていない条件で卸されたチップが使われていたのではないかと話題になっていた(過去記事)。
同記事にてリンクが貼られている過去記事より推測すると、Intelは自社の品質基準に満たないフラッシュメモリー・チップを、Intelというブランド名を利用しない条件で他のメーカーへ卸しており、Colorfulはそのフラッシュメモリー・チップを採用したSSDを、条件に反してIntelのフラッシュメモリー・チップ採用と謳って販売したと考えられます。
Colorfulはこのように販売したことが問題であると認識し、Intel製チップ採用と謳わずに販売するようになったと考えられます。
以上の考えは、あくまで個人的な推測です。
Intel以外のメーカーのフラッシュメモリー・チップを採用し、何らかの理由でチップの製造元を記載しなくなった可能性も考えられます。
SATAのモード
Windows Vistaまで
AHCIモードとIDEモードどちらがよいのか、使用するSSD、OS、ドライバによって違います。簡単に言えば速度が出る方のモードにすればよく、どちらのモードの方が速度が出るのか、実際に設定し調べる必要があります。
SSDがSerial ATA 1.0a対応の場合、AHCIモードだと速度低下が発生する場合があり、その場合はIDEモードにするとよいです。
NCQを利用するにはAHCIモードにする必要がありますが、NCQ非対応SSDであればAHCIモードにする必要がありません。
NCQ対応SSDであればAHCIモードがよいですが、利用するOSやドライバによってはNCQ利用できなくてもIDEモードの方が速度が出る場合があります。
Windows 7から
Windows 7からAHCIモードがよいです。Windows 7ではTrimが実装される等、SSDの使用を前提に開発されたので、Windows 7標準のAHCIドライバ利用かつAHCIモードでも速度が低下せず、IDEモードだと速度が低下するだけでなくTrimを利用できなくなります。
SSDの価格
価格変動
SSDが登場し始めた頃と比べると価格変動が小さいですが、激しいです。SSDが登場し始めた頃は価格が非常に高く、2008年の春頃では容量が32GBでも10万円以上でした。
それから約1年後には容量が32GBであれば約1万円まで低価格化が進みました。
ここまで価格変動が激しくなることは、もうないと思われます。
基本的に価格が下がる方へ変動しますが、逆に価格が上がる方へ変動する場合もります。
将来において価格が下がると見られるなら購入を遅らせるとよく、価格が上がると見られるなら早めに購入するとよいですが、正確に予測するのが難しいので必要な時点で買うのもありです。
為替相場の影響
SSDの価格は、為替相場の影響を受けやすいです。2017年の値上がり
いつから値上がりが始まったのかは判定が難しいですが、2017年1月にはSSDの値上がりを確認できました。2017年の冬になっても値上がりが止まる気配が見られませんでした。
為替と世界的なフラッシュメモリー不足が要因となり値上がりしました。
2017年に入る少し前に円安方向へ大きく動き、2017年を通してみると円安方向へ動き続けたわけではありませんので、世界的なフラッシュメモリー不足が主要な要因と思われます。
SSDはパソコンに限らず他のコンピューターでも使用されていますが、データセンター等にてSSDの需要が大きく伸びました。
従来から使用されてきたHDDからSSDへの置き換えが急速に進み、需要が供給を大きく超えました。
フラッシュメモリーはSSDに限らずスマートフォンのストレージ等、様々な機器に採用されていますので、いろんなところでフラッシュメモリーの需要が伸び供給不足になり、その結果SSDが値上がりしました。
SSDの保証
分解
SSDの保証は、SSDを分解すると無効になります。S.M.A.R.T.に高温が記録
SSDのメーカーによっては、S.M.A.R.T.に高温が記録されると保証が無効になる可能性があります。例えば、Crucial(クルーシャル)では「Enclosure Temperature」と呼ぶ項目を独自に定義しており、その項目に記録された値はSSDが過去に到達した最高温度であり、その温度が70度を超えると保証が無効になる可能性があります。
温度に限らず使用環境に問題があると保証が無効になる可能性があります。
SSDの普及率
PCトレンドレポート: 2017年 PCの利用に関する事実トップ 7
では、アバストのソフトウェアを利用しているユーザーから集めたデータをレポートにして公開しています。
レポートは、2017年第3四半期アバスト PC トレンド レポートと呼ばれています。
このレポートから2017年時点におけるパソコンに関する事実がわかりますが、SSDに関して以下のとおり書かれています。
SSDの普及率が意外と低い印象を受ける人もいると思われます。
この記事によると、パソコンの平均使用年数を考慮すると当然の結果とも言えるようです。
ちなみに、このレポートからパソコンの平均使用年数が5年以上であることもわかります。
パソコンの平均使用年数が意外と長い印象を受けるかもしれませんが、 政府統計の総合窓口 にて公開されている主要耐久消費財の買替え状況(2017年3月調査)によると、パソコンの平均使用年数は6.8年です。
レポートは、2017年第3四半期アバスト PC トレンド レポートと呼ばれています。
このレポートから2017年時点におけるパソコンに関する事実がわかりますが、SSDに関して以下のとおり書かれています。
今回の調査対象となった多数のユーザーのうち、SSD を使用しているのはわずか 7.4% で、6.7% のユーザーはシステム内で SSD と HDD を組み合わせて使用していました。残りのユーザー (85.9%) は従来のハード ディスクを使用しているため、低いデータ転送速度と遅いシステム速度に耐えている状態です。アバストのレポートを参考にする限り、2017年時点におけるパソコンでのSSDの普及率は14.1%です。
SSDの普及率が意外と低い印象を受ける人もいると思われます。
この記事によると、パソコンの平均使用年数を考慮すると当然の結果とも言えるようです。
ちなみに、このレポートからパソコンの平均使用年数が5年以上であることもわかります。
パソコンの平均使用年数が意外と長い印象を受けるかもしれませんが、 政府統計の総合窓口 にて公開されている主要耐久消費財の買替え状況(2017年3月調査)によると、パソコンの平均使用年数は6.8年です。
SSDとWindows
Windowsには、HDDでは有効がよいがSSDでは無効がよい様々な機能があります。Windows 7からシステムドライブがSSDの場合、自動デフラグ、スーパーフェッチ、ブートプリフェッチ、アプリケーション起動プリフェッチ、ReadyBoost、ReadyDriveが自動的に無効になります。全ての機能に当てはまるわけではありませんが、有効にしようとしてもできない機能があります。
SSDであるだけではなく、ATA8-ACS準拠のコマンドに対応している、もしくはランダム読み込み速度が8MB/sを超える条件を満たすと自動的に無効になります。この条件を満たしていても自動的に無効にならない場合があり、その場合は手動で無効にする必要があります。
Windows 7が登場後しばらくは、多くのSSDがATA8-ACSコマンドに対応していなかったので、実質的にランダム読み込み速度が8MB/s以上を満たす条件が必要でした。8MB/s以上のSSDが多くはなかったので、自動的に無効になる場合がそれほど多くありませんでした。その後、ATA8-ACSコマンドに対応し8MB/s以上あるSSDが普及し、自動的に無効になるのが当たり前になりました。
SSDであるだけではなく、ATA8-ACS準拠のコマンドに対応している、もしくはランダム読み込み速度が8MB/sを超える条件を満たすと自動的に無効になります。この条件を満たしていても自動的に無効にならない場合があり、その場合は手動で無効にする必要があります。
Windows 7が登場後しばらくは、多くのSSDがATA8-ACSコマンドに対応していなかったので、実質的にランダム読み込み速度が8MB/s以上を満たす条件が必要でした。8MB/s以上のSSDが多くはなかったので、自動的に無効になる場合がそれほど多くありませんでした。その後、ATA8-ACSコマンドに対応し8MB/s以上あるSSDが普及し、自動的に無効になるのが当たり前になりました。
SSDの基本情報
SSDの基本情報を知りたい場合は仕様を確認すればよいですが、全ての基本情報が記載されているとは限らず一部が不明な場合があります。
その場合、CrystalDiskInfoを利用すると基本情報を確認できます。
基本情報には、型番、容量、キャッシュ、インターフェースの規格、NCQ、Trim、電源投入回数、使用時間、温度等があります。
その場合、CrystalDiskInfoを利用すると基本情報を確認できます。
基本情報には、型番、容量、キャッシュ、インターフェースの規格、NCQ、Trim、電源投入回数、使用時間、温度等があります。
| キャンペーン情報(PR) |
|---|
|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |